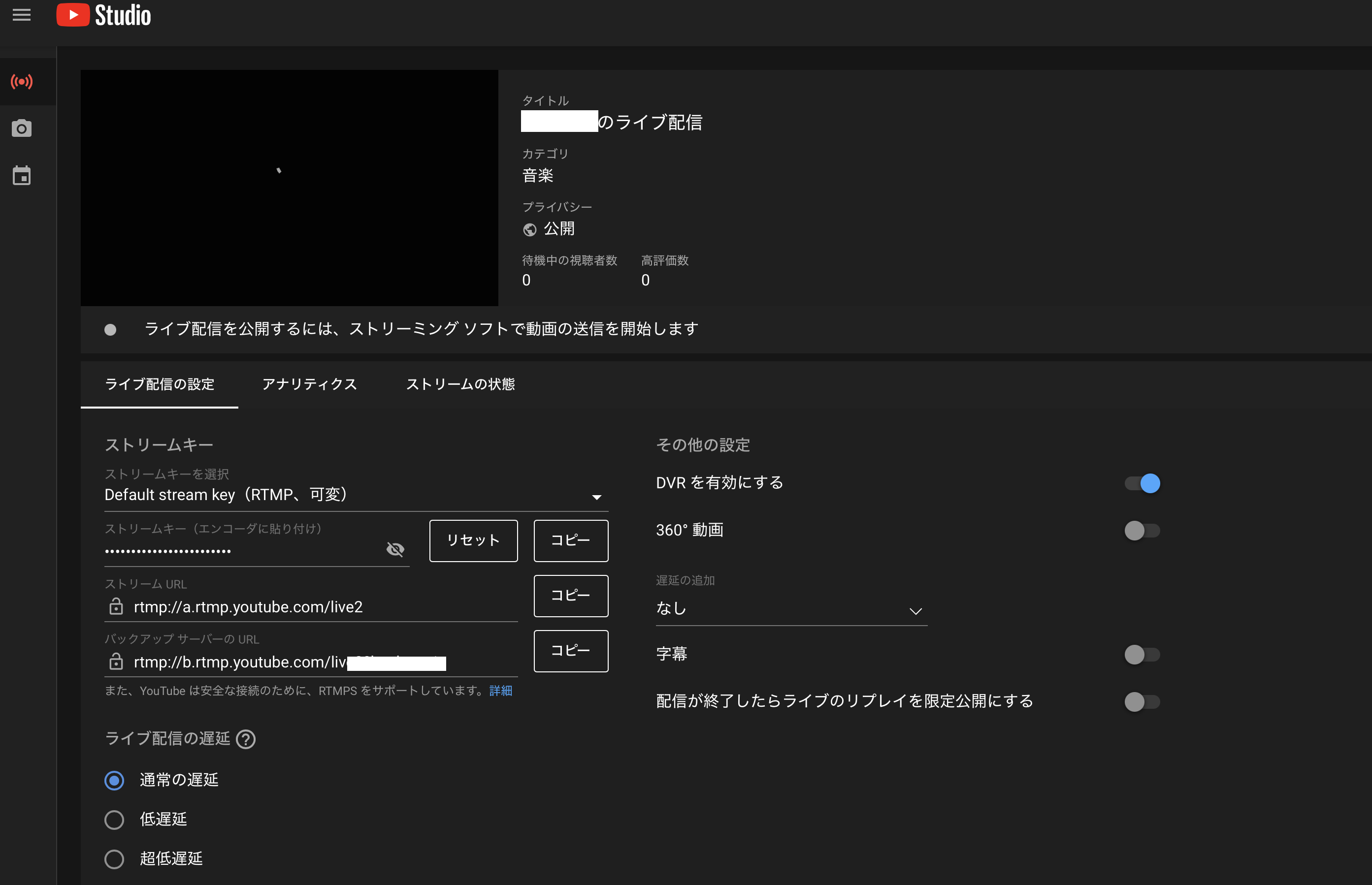自社内で映像コンテンツを制作することは可能か?

YouTubeやTikTokなどの映像コンテンツを、
制作会社に依頼すると結構なコストがかかる。
かといって個人の方にお願いするのも
クオリティーやセキュリティー、いろんな面で心配が…
そこで多くの企業の方が、自社内で作ればいいじゃないか!
と動画の内製という決断に至るケースがあります。
そこで今回は、自社内でコンテンツを作るにあたって
様々な具体的事例(失敗、成功含め) 注意点をまとめました。
まず結論から言って、
自社で制作することは可能だと思います。
絶対条件はこちらの3つ
①ある程度映像に詳しい方がいる
②専属のスタッフが配置できる
③やる気がある!
まず①ですが、やはり全くの見識がない方が
映像コンテンツをゼロから立ち上げるのは無理があります。
10分に一回壁にぶち当たり、挫折すること間違いなしです。
最低限、以下の3つが必要です。
撮影(カメラ)に関する扱いが分かる。
編集ソフトが使える
パソコン、ITに明るい方がいる
ではどの程度のスキルが必要なのか?
いきなりですが上記の条件を満たせるかどうか?
簡単なクイズを出してみましょう!
問1 カメラで記録メディアを初期化、
フォーマットしてください
問2 フルHDの画面サイズは?
問3 1TBは何GB?
この問いに即答できない、
説明されても理解出来る気がしないし、
聞く気もないと言う方は
確実にやめた方が良いでしょう
② ①で挙げたような条件に合うスタッフが専属でいらっしゃること。
出来れば複数が望ましいでしょう。
他の業務と掛け持ちや、兼務ではほぼ間違いなく破綻しています。
映像はとにかく時間がかかります。
プロとアマチュアの方の決定的な差は
この作業にかける時間です。
普通の方が丸一日かかることを
熟練の技術と知識で 数時間で終わらせることができるから
仕事として成立するわけです。
③何よりもやる気と興味、 根気がないと続きません。
動画コンテンツは継続的に更新すること がマストですので
何よりもこの継続が難しいと思います。
好きこそ物の上手なれとは言いますが、
好きだけでは続かないのが現状です。
逆にこのやる気さえ人の何倍もあれば
技術や知識は後からついてくることもあります。
私個人としましては、学習と経験によって
スキルを身に付け、
自分でどんどんできるようになることは
企業にとっても非常に良いことと思います。
次回は、そんな自社制作化に成功している
企業様の具体例と、苦戦している企業様の例を
具体的にご紹介したいと思います。
制作会社に依頼すると結構なコストがかかる。
かといって個人の方にお願いするのも
クオリティーやセキュリティー、いろんな面で心配が…
そこで多くの企業の方が、自社内で作ればいいじゃないか!
と動画の内製という決断に至るケースがあります。
そこで今回は、自社内でコンテンツを作るにあたって
様々な具体的事例(失敗、成功含め) 注意点をまとめました。
まず結論から言って、
自社で制作することは可能だと思います。
絶対条件はこちらの3つ
①ある程度映像に詳しい方がいる
②専属のスタッフが配置できる
③やる気がある!
まず①ですが、やはり全くの見識がない方が
映像コンテンツをゼロから立ち上げるのは無理があります。
10分に一回壁にぶち当たり、挫折すること間違いなしです。
最低限、以下の3つが必要です。
撮影(カメラ)に関する扱いが分かる。
編集ソフトが使える
パソコン、ITに明るい方がいる
ではどの程度のスキルが必要なのか?
いきなりですが上記の条件を満たせるかどうか?
簡単なクイズを出してみましょう!
問1 カメラで記録メディアを初期化、
フォーマットしてください
問2 フルHDの画面サイズは?
問3 1TBは何GB?
この問いに即答できない、
説明されても理解出来る気がしないし、
聞く気もないと言う方は
確実にやめた方が良いでしょう
② ①で挙げたような条件に合うスタッフが専属でいらっしゃること。
出来れば複数が望ましいでしょう。
他の業務と掛け持ちや、兼務ではほぼ間違いなく破綻しています。
映像はとにかく時間がかかります。
プロとアマチュアの方の決定的な差は
この作業にかける時間です。
普通の方が丸一日かかることを
熟練の技術と知識で 数時間で終わらせることができるから
仕事として成立するわけです。
③何よりもやる気と興味、 根気がないと続きません。
動画コンテンツは継続的に更新すること がマストですので
何よりもこの継続が難しいと思います。
好きこそ物の上手なれとは言いますが、
好きだけでは続かないのが現状です。
逆にこのやる気さえ人の何倍もあれば
技術や知識は後からついてくることもあります。
私個人としましては、学習と経験によって
スキルを身に付け、
自分でどんどんできるようになることは
企業にとっても非常に良いことと思います。
次回は、そんな自社制作化に成功している
企業様の具体例と、苦戦している企業様の例を
具体的にご紹介したいと思います。